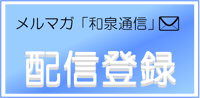気泡緩衝材エアセルマットの株式会社和泉
|
和泉'sブログ このサイトは、和泉の今をお届けするブログサイトです |

和泉では、名古屋春日井工場においてISO 14001(環境マネジメントシステム:EMS)を2007年4月に取得しました。取得から18年が経過し、私たちは長期にわたり、環境への配慮を継続的に企業活動に取り入れ、改善していく仕組みを運用しています。
和泉におけるISO取得の取り組みを振り返る
ISO 14001の取得を進めた2007年当時は、社会的にISO認証への関心が高まる「ISOブーム」とも呼べる時期でした。ISO認証の有無が取引条件となるケースもあり、取得は事業継続の上でも重要な要素だったと記憶しています。
取得にあたっては、複数の部署から担当者を選出しチームを組成し、外部コンサルタントの支援を受けながら進めました。当時のメンバーからは、当初は専門用語の理解に苦労したという声も聞かれましたが、環境に対する具体的な取り組みとして、廃棄物の削減や分別などを徹底しました。
その結果、産業廃棄物費用の削減や、これまで廃棄物として処理していたものを有価物として買い取ってもらえるようになるなど、環境面だけでなく費用面での具体的なメリットも得ることができました。
一方で、マネジメントシステムの運用を続ける中で、活動内容がマンネリ化し、新たな取り組みテーマを見つけることに課題を感じる場面も出てきました。これは、ISOに限らず、継続的な改善活動を行う多くの組織が直面する共通の課題かもしれません。
ISOとは
ここで改めて、ISOについて確認しておきましょう。
ISO(国際標準化機構:International Organization for
Standardization)は、1947年に設立された非政府組織で、スイスのジュネーブに本部を置いています。その主な活動は、製品やサービス、技術、マネジメントシステムなどに関する国際的に通用する標準規格(ISO規格)を制定することです。これにより、国際的な取引をスムーズにし、品質や安全性を確保し、環境保護などの共通課題に対応することを目指しています。
私たちの身近にもISO規格は存在します。
例えば、非常口のマーク(ISO 7010)や、クレジットカードなどのサイズ(ISO/IEC 7810)などが挙げられます。これらは「モノ規格」と呼ばれており、国際的に統一されていることで、私たちは国境を越えても混乱なく様々なサービスや製品を利用できています。
マネジメントシステム規格としてのISO
ISO規格には、製品そのものに関する「モノ規格」の他に、組織の活動や管理の仕組みに関する「マネジメントシステム規格」があります。和泉が取得しているISO 14001や、品質に関するISO 9001などがこれにあたります。
マネジメントシステム規格は、組織が特定の目的(環境保護や品質向上など)を達成するために、方針を定め、目標を設定し、計画を実行し、結果を確認し、改善するという一連の「仕組み」を構築・運用するための要求事項を定めています。これらの規格に沿ってマネジメントシステムを構築し、第三者機関による審査に合格することで認証を取得できます。
ISOとSDGsの違い
近年、環境や社会への意識の高まりとともに「SDGs(持続可能な開発目標)」という言葉をよく耳にするようになりました。SDGsもISO 14001が対象とする環境側面と関連が深いため、混同されることもありますが、両者には明確な違いがあります。
SDGsは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた、2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲットです。貧困、飢餓、教育、気候変動など、地球規模の幅広い課題に対する国際社会共通の目標であり、企業や個人を含む全ての主体が達成に向けて取り組むことが期待されています。SDGs自体には、ISOのような国際的な認証制度はありません。
ただし、日本国内では県や市などの自治体やSDGs関連団体による独自の認証・認定制度は存在します。しかし、こういった独自認証・認定制度の多くは、「SDGsに取り組んでいますよ」という企業姿勢を示す側面が強く、ISOのような厳格な第三者審査を伴うものではないようです。
対してISO 14001は、組織が自らの活動、製品及びサービスによって生じる環境負荷を低減し、環境パフォーマンスを向上させるための「環境マネジメントシステム」に関する国際規格です。
ISO 14001は、組織が環境目標を設定し、その達成に向けた計画を実行し、継続的に改善していくための具体的な「仕組み」の構築と運用に焦点を当てています。そして、この仕組みが規格の要求事項を満たしているかどうかが第三者機関によって審査され、認証が付与されます。
つまり、SDGsは「持続可能な社会を実現するための目標」であり、ISO 14001は「環境側面において持続可能な取り組みを行うための具体的なマネジメントシステムのツール」という違いがあります。
ISO 14001の取得・運用は、企業がSDGsの目標年である2030年に向けた環境関連の目標達成に貢献するための一つの有効な手段となり得ます。
ISOの現状と今後の展望
ISO認証の取得状況は、規格の種類によって異なる傾向が見られます。
ISO認証を取得した組織数の年別推移統計について、国内における総数をまとめた、信頼のおける統計は残念ながら見つけることができませんでした。そこで、認証機関のひとつである公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)が公表している、同協会におけるISO 9001およびISO 14001の取得企業数推移を挙げましょう。
※いずれもJAB事業報告書より認証組織数を抽出
※年度の異なる事業報告書によって認証組織数が異なる場合は、発行年度が新しい事業報告書の数値を正しいものとして記載
※これは国内におけるISO 9001およびISO 14001の認証組織数の総計ではないこと、そして認証機関によって認証ごとの取得数は異なるため、国内における傾向をそのまま示したものとは断じられないことをご留意ください
この統計を見る限りでは、ISO 9001、ISO 14001ともに、取得組織数は減少傾向にあります。
今年の審査時にISO担当審査員から情報交換をする機会があったのですが、以前は県庁なども多くがISOを取得していたものの、今はISOを更新せず、返上するところも多くなって来ているとのこと。
費用や工数負担も大きいですし、あるいは取引先などからの要求(ISO認証の有無が取引条件とするなど)が少なくなってきていることも理由なのでしょう。
また、ISO 9001で構築したマネジメントシステムの仕組みを自社向けに変更して、独自で管理をする企業が増えて来ているとも聞きます。これは、ISO認証の維持にかかるコストを削減しつつ、自社の実情に合わせた柔軟な運用を目指す動きと考えられます。
和泉にもISO審査会社から営業の電話がかかってくるようになっています。これは認証返上による顧客減少を背景とした、審査会社の営業活動の強化を示唆しているのかもしれません。
しかし一方で、当社のISO担当審査官によれば、環境意識の高まりを背景としたISO 14001の取得組織数は増加していると言います。
このあたりはJABの統計結果とは異なりますが、確かに統計結果を診るとISO 14001における取得組織数の減少傾向は穏やかになっています。
最近話題となっている気候温暖化、あるいは異常気象といった要素が、「より積極的に環境問題に取り組もう」「ISO 14001を通じて、環境への取り組みをアピールしたい」とする企業のモチベーションにつながっているのかもしれません。
引き続き、和泉も環境問題を考慮しつつ企業活動を進めていきたいと考えています。
(品質・データ管理部 岡谷)