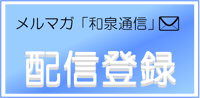気泡緩衝材エアセルマットの株式会社和泉
|
和泉'sブログ このサイトは、和泉の今をお届けするブログサイトです |
2022年から2025年にかけて段階的に施行される育児・介護休業法(以下、育介法)が改正されます。
この育介法、なかなか厄介です。
- 法律が多岐にわたり、またその対応も簡単ではないこと
- 単に法令遵守だけを行うと事業遂行に支障が生じるため、業務改善にも取り組まなければならないこと
- 育介法への対応は、いわゆる「子持ち様」問題など新たな課題を引き起こしており、従業員の意識改革にも取り組まなければならないこと
本稿では、育児休暇にフォーカスし、育介法を取り巻く課題を考えます。
育児・介護休業法 改正のポイント
今回の育介法改正は、特に「男性育休の促進」と「企業取り組みの透明化」に焦点を当てています。これらに関係する主な改正点をピックアップします。
| 項目 | 改正前(~2022年) | 改正後(2022年10月~2025年4月) |
| 男性の育休 | 育児休業(原則1回)のみ | 「産後パパ育休」の新設(出生後8週間以内に4週間まで・2回分割可) |
|
育児休業の分割取得(男女とも2回まで分割可) |
||
| 育休取得の周知 | 特になし | 個別の制度周知・取得意向確認の義務化(2022年4月~) |
| 育休取得状況の公表 | 従業員1,000人超の企業(努力義務) | 従業員1,000人超の企業(義務化)(2023年4月~) |
| 従業員300人超の企業(義務化)(2025年4月~) | ||
| 両立支援措置 | 3歳未満の子が対象 | 3歳未満の子:テレワークの努力義務 |
| 小学校就学前の子:短時間勤務、テレワーク等の代替措置の拡充(2025年4月~) |
※詳しくは、厚労省の「育児・介護休業法について」および「産後パパ育休」をご覧ください。
例えば男性の場合、産後パパ育休も含めると子どもが1歳になるまでに最大4回、業務の繁閑や家庭の状況に合わせて柔軟に休業を取得できる制度設計となりました。
つまり、「育児のために長期間休業する」というだけではなく、「家庭や育児の都合に合わせ、短期間の休業を何度も取得する」という選択肢を可能にしたのです。
【ジレンマその一】代替要員の確保と属人化という経営課題
育児休業者が出れば、その職場では誰かがその穴埋めをしなければなりません。
「女性、外国人材の活躍に関する調査」(2022年9月、日本商工会議所)によれば、男性育休促進の課題として、52.4%が「専門業務や属人的な業務を担う社員の育休時に対応できる代替要員が社内にいない」と回答しています。さらに35.7%が「採用難や資金難で育休時の代替要員を外部から確保できない」としており、半数以上の企業が「内部にも外部にも代替手段がない」という八方塞がりの状態です。
さらに言えば、「男性社員自身が育児休業の取得を望まない」という回答も28.8%ありました。これは少し古い調査結果なので、今同様の調査を行えばもう少し違う結果が出るかもしれませんが。
いずれにせよ、この結果を単なる人手不足の問題と捉えるのは間違いでしょう。本質的な病巣は、特定の個人がいなければ業務が回らない業務の属人化という課題を長年放置してきた結果と考えるべきです。
育介法の改正は、「代替要員の補充」という対症療法だけではなく、「業務プロセスの抜本的改革(属人化の解消)」という体質改善を企業に求めています。
「子持ち様」問題に見る、従業員間の不公平感
「子持ち様」というネットスラングをご存知でしょうか?
これは、育児を理由に遅刻・早退や時短勤務、突発的な欠勤をする「子持ち」の従業員のことを、そのしわ寄せを被る従業員が揶揄・批判するために用いる言葉です。
例えば、「職場の『子持ち様』、『子どもが熱を出した!』って早退したけどさ、その尻拭いをさせられる私の苦労も考えてよね」といったような使われ方をします。
育児をしていれば子どもの都合で遅刻・早退や欠勤をせざるを得ないケースはどうしても発生します。またこういった権利が法律で認められている以上、これを行使する人を批判することは妥当ではありません。
しかしだからと言って、「子持ち様」と揶揄する人──すなわち休業者の業務を一方的に負担させられる「周囲の従業員」──が、深刻な不満と疲弊を抱えていることから目を背けてはなりません。
育介法が目指す理想を本当の意味で実現しようとするならば、現場のオペレーション(人員配置や業務プロセス)の改善は必須です。このしわ寄せに対する評価や手当といったケアを企業が怠った結果、負担を強いられる側の不公平感が蓄積し、従業員間の分断を生み出しているのです。
「育休社員の『肩代わり手当・制度』の実態調査」(2025年9月9日、MS-Japan)は、この実態を浮き彫りにしています。育休や時短社員の業務を代替・支援した経験がある人のうち、実に77.6%が業務代替に「課題を感じたことがある」と回答しています。
- 「業務量が増え、負担や疲労が大きくなった」65.4%
- 「ワークライフバランスが崩れた」「通常業務に支障が出た」32.1%
さらに、「評価や報酬が不十分」(29.5%)、「業務分担の偏りに不満を感じた」(25.6%)という回答からは、育児休暇等によって生じる現場の負担を、経営側がフォローすることなく、現場に丸投げしている実態が伺えます。
実際この調査では、業務を代替する社員への「肩代わり手当・制度」または「人員配置」という何らかの対応が「ある」企業は、わずか35.3%に過ぎませんでした。
ちなみに「子育てに関するアンケート調査結果」(2024年10月17日、明治安田生命)では、育休を取得した男性の割合が33.4%と過去の最高値を更新した一方で、職場復帰後に41.5%の男性が「気まずいと感じた」と答えています。
この結果は、「子持ち様」問題で顕在化した、「休んだ私の仕事は誰が肩代わりしてくれたの?」という負い目からくるものでしょう。
「男性の育休は無意味?」論争の勃発
企業の対策不備に加えて、もう1つ、育休を取得する男性従業員側の意識とスキルという課題が生じています。
改正育介法では、男性が育児の当事者となることを求めていますが、現実には育休を「取得すること」自体が目的化し、育児に参加しない男性の存在が課題としてクローズアップされつつあります。
筆者は平均よりもだいぶ遅く子どもを授かりました。そのおかげで先輩パパ・ママたちからいろいろなアドバイスを貰えたのですが、中には「私はおむつ交換や沐浴をしたことがなかったが、今考えるとやっておくべきだったのであなたも積極的に手伝ったほうが良い」といった男性の友人からのアドバイスが複数ありました。
当人たちは親切のつもりでアドバイスしたのでしょうが、「今どき、育児をしない男性がこれほどいるのか!?」と驚いたものです。
家事(例:料理、洗濯、掃除)や育児(例:沐浴、寝かしつけ)を行わず、育児の戦力として機能しない「取るだけ育休」は、家庭にも職場にも悪影響を生じかねません。
- 家庭内の不満
パートナーの不満が蓄積し、家庭内不和につながる。
- 職場への悪影響
育休中に実質的な育児経験を積めなかったため、復帰後に育児との両立に苦慮する同僚への理解が深まらない。
- 周囲の誤解を助長
「育休=休養」であったかのような実態が周囲に伝われば、「子持ち様」問題のようなしわ寄せに耐えている同僚の不公平感をさらに煽り、「やはり男性育休は無意味だ」というハラスメント(イクハラ)の温床となりかねない。
もはやイクメン(※子育てに参加する男性)は、褒められる対象ではなく、当然のことと男性は意識を変えるべきでしょう。
【まとめ】改正育介法がもたらすメリットとデメリット
メリット
- 従業員エンゲージメントの向上
制度利用者および将来の利用者が「働き続けられる会社」と認識し、組織への愛着やコミットメントが向上すること。
- 人材の獲得と定着
「両立支援」に取り組む姿勢を公表することが、採用市場における強力なアピールとなり、優秀な人材の確保と離職率の低下につながること。
- 組織風土の改善
全社で「お互い様の精神」が醸成され、コミュニケーションが活性化すること。
- 業務改革の強制力
育休による強制的な欠員が、長年放置されてきた業務の属人化を解消し、多能工化や業務標準化を進める絶好の機会となること。
デメリット
- 従業員エンゲージメントの低下
対策を怠った場合、業務のしわ寄せが集中する従業員の不公平感と疲弊を招き、組織全体のエンゲージメントが著しく低下すること。
- 組織内の分断
制度利用者(子持ち様)と周囲の従業員との間に対立構造が生まれ、組織の一体感が失われること。
- オペレーションの混乱
短期・反復的な育休に対応できず、業務プロセスが停滞・破綻すること。
- 「取るだけ育休」による制度の形骸化
男性育休が実質的な育児参加につながらない場合、制度への誤解や不信感が社内に広がること。
育介法の改正は、岸田文雄首相が在任時に掲げた「異次元の少子化対策」および「こども未来戦略」の中核的施策に位置付けられるものです。結果的に、旧来の企業経営に改善を促すというのは、言わば副作用なのでしょうが...、この副作用が大きすぎることから、困惑する企業も多くいます。
言ってみれば、国は制度だけを用意し、その制度が求める対策は企業側に丸投げしている状態と言えます。しかし、これは考えようによっては、「企業側がこの法改正にきちんと対応をすれば、新たな企業価値を獲得できるチャンスである」とも考えられます。
例えば、育休の取得状況をきちんと公開し、これに対するKPIも詳らかにすれば、就職希望者は安心するでしょう。
例えば、本稿で挙げたような属人化や「子持ち様」問題、男性の「取るだけ育休」問題に対する対応策を社内外を問わず公表できる企業は、信頼を勝ち得ることができるはずです。
「ピンチはチャンス」と言います。改正育介法は、まさしく一種の試金石であり、「このピンチを企業価値向上に繋げられる企業」とそうでない企業の明暗が分かれるきっかけとなりそうです。