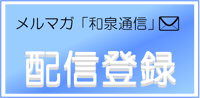気泡緩衝材エアセルマットの株式会社和泉
|
和泉'sブログ このサイトは、和泉の今をお届けするブログサイトです |

これまでのWebマーケティングが転換期を迎えています。
「当社Webサイトの閲覧数が大幅に減っている!!」──こんなWeb担当者の悲鳴が、各所から聞こえてくるようになりました。
筆者は、Yahoo!ニュースやNewsPicksなど、複数のWebメディアや(和泉以外の)企業オウンドメディアで執筆をしています。特にWebメディアでは閲覧数(ページビュー)や訪問者数の減少は顕著で、3割、あるいは4割以上減ったというメディアもあります。
そんな中、メルマガ「和泉通信」を配信する「和泉'sブログ」では、閲覧数は減っているものの、その減少幅は1割前後で、他メディアと比べると影響はわずかです。
なぜなんでしょうね?
実はこの現象には、生成AIなどの普及拡大が影響しています。
「SEOは死んだ!?」、今までのやり方が通用しなくなった理由
これまで、Webマーケティングの基本と言えば、「SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)」でした。
SEOとは、Googleなどで検索された時に、自社のWebサイトが上位に表示されるように工夫するマーケティング手法です。検索上位に表示されれば、多くの人がクリックしてサイトを訪れてくれる(=トラフィックが増える)と期待できます。特に、ユーザーの疑問や悩みに答えるような役立つ記事(コンテンツ)を作成し、それを通じて集客を図る手法を「コンテンツSEO」と呼び、近年では多くの企業やWebメディアが取り組んできました。
SEOは、長く──筆者の感覚だと、2000年初頭から20年近く──Webマーケティングにおける常識であり、基本であり、王道でした。
SEOを揺るがし始めたのが、AI技術、特にChatGPTのような生成AIや、Google検索に導入された「AI Overviews(AIによる要約回答)」の登場です。
AI Overviewsの例。
Googleでは、検索キーワードに対し、AIが生成した要約回答が表示されるようになりました。
※画像はクリックで拡大します
これらの新技術により、私たちがインターネットで情報を探す方法が根本から変わりつつあります。
AIは、ユーザーが知りたいことを、検索結果のページで直接、文章でまとめて提示してしまいます。ユーザーはAI Overviewsを読むだけで満足してしまい、検索結果に記された個別のWebサイト(※便宜上、本記事では「検索結果サイト」と呼称します)をわざわざクリックして訪問しなくなってしまったのです。
断言しますが、検索結果サイトで得られる情報量と、AI Overviewsによる情報量には大きな差があります。AI Overviewsは、あくまで要約です。文字数も情報量も、また求める検索キーワードに対する周辺情報や説明も、検索結果サイトとは比べ物になりません。
しかし多くの場合、AI Overviewsによる要約で満足できるケースが多いのでしょうね。
このように、Webサイトへの訪問者数が激減する「トラフィック日照り」とも呼ぶべき深刻な事態が起きています。
データが示す「クリックされない」現実
これは感覚的な話ではなく、実際のデータにも表れています。
- ゼロクリック検索の増加
AIが導入される以前から、検索結果の58%はクリックされずに終わっていました(ゼロクリック検索)。AIが直接回答を提示するようになり、この割合はさらに悪化すると見られています。
- クリック率の壊滅的低下
2025年9月に発表されたSeer Interactiveの詳細な調査では、情報提供型の検索(「〇〇とは?」など)でAIの回答が表示された場合、検索結果のクリック率(CTR)が61%も激減したという報告があります。
- メディアサイトへの大打撃
Digital Content Next (DCN) が2025年5月から6月にかけて実施した調査によると、主要なメディアサイトのGoogle検索からの流入トラフィックが、前年比で中央値10%減少し、特にライフスタイル系メディアでは14%もの減少が記録されました。
これは特に、企業やWebメディアが「役立つ情報」として提供してきた「〇〇の方法」といった記事(コンテンツSEO)が、AIによって代替され、従来のSEOという手法が成立しなくなりつつあることを示しています。
「和泉'sブログ」の閲覧者数が大きく減少しなかった理由
では、なぜ「和泉'sブログ」では、他のWebサイトやメディアほど大きな閲覧者数の減少が起きなかったのでしょうか?
最大の理由は、「SEOよりもエンゲージメント」こそが「和泉'sブログ」の基本方針であるためと考えています。
まず、「和泉'sブログ」ではSEOをあまり意識していません。その理由は以下のとおりです。
- 当社のマーケティング戦略は、まずメルマガ「和泉通信」が優先で、「和泉'sブログ」はメルマガのアーカイブ的位置付けとしていること。
- メルマガの読者は、当社の大切なお客様やお取引様が中心。よってリアルコミュニケーションを補完するエンゲージメントツールとして、メルマガを配信していること。
- このために、「和泉'sブログ」のコンテンツ(=メルマガ「和泉通信」のコンテンツ)は、読者の皆様にとって有用な情報提供コンテンツと、特に営業担当者を中心とした和泉社員とのエンゲージメントをアピールするコンテンツという2本の柱を軸として構成していること。
SEOを基本戦略とする企業オウンドメディアでは、どうしても自社製品・サービスに関連するキーワードの解説記事や、宣伝記事が中心となります。ただ、こういった記事ばかりだと、読者の方も息がつまるというか...、私どもはもっと人間味あふれる部分も含めて、皆様とのエンゲージメントを築きたいと考えています。
もっとも、そうでなければ今回配信した「名古屋城エリアが変わる!紅葉の名所・名城公園とIGアリーナ、そして未来の姿」のような記事は配信しませんよね。
一応申し上げると、当社の取り組みは、AI Overviewsなどの影響を戦略的に先読みしたものではありません。そもそも、こんな状況が発生するなど誰も予想していなかったことでしょう。
「和泉'sブログ」において、他メディアほどの閲覧者数減少が発生しなかったのは、「SEOよりも、お客様・お取引様とのエンゲージメントをより重視する」という基本方針が思いがけず功を奏した結果論なのです。
SEOに代わる、「一次情報」や「実体験」のコンテンツ
従来のコンテンツSEOは、「検索されそうなキーワードを網羅した、質の高いまとめ記事や解説記事」を作ることが基本でした。しかし皮肉なことに、既存の情報をまとめて「網羅的な記事」を作ることは、生成AIがもっとも得意とすることです。
Google自身も「AIが作ったか、人間が作ったか」は問わず、内容が高品質であれば評価すると公言しています。
つまり、人間が苦労して作ってきたSEO対策記事は、AIに学習データとして消費されるだけで、もはや以前のような「訪問者を集めるチカラ」を失いつつあります。
代わりに注目されているのは、AIには生み出せない情報です。
AIは、(主として)インターネット上にあふれる既存の情報を再構成することはできますが、ゼロから何かを体験することはできません。
奇しくもこの流れと呼応するように、Googleは検索品質の評価基準を見直しています。
Googleは以前から「E-A-T(Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性)」という基準を重視していましたが、2022年末、これに「E(Experience:経験)」を加え、「E-E-A-T」という新たな基準を採用しました。
AIには模倣できない「商品を実際に使ってみた体験談」、「独自に行った調査データ」、「特定の場所を訪れた記録」 といった「一次情報」と「実体験」こそが、これからのWebコンテンツにおいて唯一無二の価値を持つ、というGoogleからの明確なメッセージとも読み取れます。
SEO至上主義に感じていた違和感
2004年のことです。
筆者は、当時急速に注目を集め始めていたSEOマーケティングを行う会社の採用面接を受けたことがありました。
面接時、この会社の社長は自社の事例としてステーキを売りにするある飲食チェーン店のSEOを実施したことを説明しました。しかし、当時はWebサイト関係には素人だった筆者の目から見ても、この飲食店のWebサイトにはさまざまな違和感──例えばデザインや文章などの点で──を感じました。
当時は、検索エンジンの能力がまだ未熟でした。そのためSEOを追求すると見た目や文章に違和感が生じるのが常でした。当時の流儀に従えば、例えばこのような文章が「SEO的に優れた文章」とされていました。
「当店のステーキは、ステーキ用に特別に開発されたステーキ牛を用いています。そのため、『ステーキ特有の臭みが嫌』『ステーキの固さが気になる』といったステーキ嫌いのお客様にも美味しく食べていただけるステーキとなっています」
「『ステーキ』って連呼しすぎでしょう...」と思いませんか?
こういった、読みやすさ等を無視し、Webサイト訪問者の違和感を放置してでも、小手先のテクニックを求めるSEO対策は、検索エンジンの進化とともに薄れていきました。誤解を恐れずに言えば、「より良いコンテンツを訪問者に届けたい」というGoogle、Yahoo!といった検索エンジン側の試行錯誤の結果のひとつがコンテンツSEOと考えられます。
AI Overviewsや生成AIは、小手先の施策で結果を求めるWebマーケッターたちと、検索エンジンの間で繰り広げられた競争の歴史がもたらした結果です。とは言え、AI Overviewsの開発と提供はGoogleの囲い込み施策ですから、ちょっと行き過ぎた感じはあります。
当社は「"ほんもの"の責任」というキャッチコピーを掲げています。現在の状況は、Googleら検索エンジン側が、奇しくも「ほんもの」を追求し、Webサイト訪問者により良い検索体験を届けたいという願いが生み出したものと考えるべきでしょう。