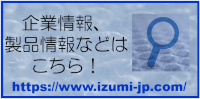気泡緩衝材エアセルマットの株式会社和泉
|
和泉'sブログ このサイトは、和泉の今をお届けするブログサイトです |
クイズです。
以下に挙げた内容は、企業同士の営業活動においてありがちな行為です。
この中で、2026年から新しくなる取適法(旧:下請法)に違反する可能性があるのはどれでしょうか?
- 極めて短いリードタイムで見積書提出を求める行為
- 通常納期よりも短期間での納品を求める行為
- 深夜・早朝など営業時間外に連絡し、返事を急かす行為
- 製品サンプルなどを強制的かつ無償で提供させる行為
- 自社製品・サービスの利用を要求する行為
実はこれら、すべて法律に抵触する可能性があります。その理由は記事の最後に解説しましょう。
今回は、分かっているようで分かっていない、この大切な法律について和泉通信流に解説します。
取適法(旧 下請法)の目的は?
ビジネスの世界では、仕事を発注する側(注文する側)と受注する側(仕事を受ける側)がいます。特に、大きな会社が中小企業に仕事を発注する場合、どうしても発注する側の立場が強くなりがちです。
このような力関係の差から、受注する側が不利な条件を押し付けられることのないように、公正な取引のルールを定めたのが下請法です。
そして、この下請法は「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)と名称を変えて、2026年1月1日に施行されます。
これほど大規模な改正は約20年ぶりのことです。
「中小受託取引適正化法」という新しい名前には、発注者と受注者が「下請け」という上下関係ではなく、対等なパートナーであるべきだという大切なメッセージが込められています。
この法律の大きな目的は、「取引の公正化」と「受注する中小企業の利益を守ること」です。
例えば、代金の支払いを不当に遅らせたり、一方的に金額を値切ったりするような行為を防ぎ、中小企業が安心して技術や品質の向上に力を注げる環境を作ることが、日本経済全体の成長につながるという考えに基づいています。
「優越的地位の濫用」と取適法の関係
独占禁止法には、「優越的地位の濫用」という概念があります。
独占禁止法では、取引で有利な立場にある事業者(優越的地位にある側)が、その立場を利用して相手に不当な不利益を与える「優越的地位の濫用」を禁止しています。
「優越的地位」とは、単に会社の規模が大きいだけでなく、取引相手がその事業者との取引に著しく依存しているなど、取引条件の設定に大きな影響力を持つ立場を指します。この立場を利用して、協賛金を不当に要求したり、自社製品の購入を強制したりすることが「濫用」にあたります。
取適法は、まさにこの「優越的地位の濫用」が起こりやすい特定の取引類型と事業者規模を抽出し、禁止行為を具体的に定めた特別法と位置づけられます。つまり、取適法の対象となれば、「優越的地位にあるかどうか」を個別に判断するまでもなく、定められた禁止行為は直ちに違反となります。
裏を返せば、取適法対象外の取引であっても、不公正な取引は独占禁止法の「優越的地位の濫用」として問題になる可能性が常にあります。そのため、すべての企業にとって公正な取引を心がけることが重要です。
取適法違反となる取り引きとは?
取適法が適用されるかどうかは、「取引の内容」と「お互いの会社の規模」というふたつの条件で決まります。どちらの条件にも当てはまる場合、自ずと取適法のルールを守る必要があります。
取適法対象となる「4つの取り引き」
取適法の対象となるのは、主に以下の4種類の仕事のやり取りです。
-
製造委託
製品の販売や製造を行っている会社が、その製品や部品の仕様(デザイン、品質、ブランドなど)を決めて、他の会社に作ることをお願いする場合です。
具体例
スーパーが自社ブランド(PB)のお弁当の製造を食品メーカーに依頼するケース
自動車メーカーが、車のエンジン部品の製造を部品メーカーに依頼ケース など
-
修理委託
製品の修理を請け負っている会社が、その修理作業を他の会社にお願いする場合です。
具体例
自動車ディーラーがお客様から預かった車の板金塗装を、専門の修理工場に依頼するケース など
-
情報成果物作成委託
ソフトウェア、テレビ番組、デザイン、設計図などの「情報」を作ることを仕事にしている会社が、その作成を他の会社にお願いする場合です。
具体例
テレビ局が、放送するドラマの制作を番組制作会社に依頼するケース
建設会社が、建物の設計図面の作成を設計事務所に依頼するケース など
-
役務提供委託
運送やビルメンテナンス、情報処理といったサービス(役務)の提供を仕事にしている会社が、そのサービスの一部を他の会社にお願いする場合です。
具体例
運送会社が引き受けた荷物の配送の一部を、別の運送会社に依頼するケース など
取適法対象となる「お互いの会社の規模」
上記の取引に加えて、発注側(委託事業者)と受注側(中小受託事業者)の会社の規模が以下の基準に当てはまる場合に、この法律が適用されます。2026年の改正で、従来の「資本金」基準に加えて「従業員数」の基準が追加され、対象範囲が大きく広がりました。
| 取引の種類 | 発注側(委託事業者)の規模 | 受注側(中小受託事業者、個人事業主を含む)の規模 |
|
①製造委託・修理委託 ②プログラム作成 ③運送・倉庫保管・情報処理サービス |
資本金3億円超 または従業員300人超 |
資本金3億円以下 または従業員300人以下 |
|
資本金1千万円超 ~3億円以下 |
資本金1千万円以下 | |
|
④上記以外の情報成果物作成 (デザイン、コンテンツ制作など) ⑤上記以外のサービス提供 (ビルメンテナンスなど) |
資本金5千万円超 または従業員100人超 |
資本金5千万円以下 または従業員100人以下 |
|
資本金1千万円超 ~5千万円以下 |
資本金1千万円以下 |
発注側(委託事業者)に課される4つ義務と、13の禁止行為
取適法では、発注側(委託事業者)に、取引を公正に進めるための4つの基本的な義務と、13の禁止行為が課せられます。
委託事業者、4つの義務
-
書面交付義務
発注する際には、仕事の内容、金額、納期、支払日などを詳しく書いた書面を、すぐに渡さなければなりません。口約束による「言った・言わない」のトラブルを防ぐための最も大切なルールです。
ちなみに、「とりあえず進めておいて」はNG!
発注側の担当者らが「正式な発注書は後で出すから」と言って、具体的な条件を曖昧にしたまま口頭やメールで作業を依頼するのは、この義務に違反します。後から「そんな条件では聞いていない」というトラブルの原因になり、発注側が不利な立場に置かれるリスクもあります。
-
支払日を決める義務
製品やサービスを受け取った日から60日以内で、できるだけ短い期間内に支払日を決めなければなりません。
-
書類を作成・保存する義務
取引の記録を書類として作成し、2年間保存しなければなりません。これにより、後から取引内容を確認できるようになります。
-
遅延利息を支払う義務
もし支払日までに代金を支払えなかった場合は、遅れた日数に応じて年率14.6%という高い利率の遅延利息を支払わなければなりません。
委託事業者、13の禁止行為
発注側(委託事業者)が、その強い立場を利用して受注側(中小受託事業者)に不利益を与えることを防ぐため、以下の13の行為が具体的に禁止されています。
たとえ受注側が同意していても、それが実質的に強制されたものであれば違反となります。
-
受け取りを拒否すること
受注側に責任がないのに、自社の都合(「在庫が増えすぎた」「計画が変わった」など)で、発注した製品の受け取りを拒否してはいけません。
-
代金の支払いを遅らせること
決めた支払日までに代金を支払わないことは禁止です。「会社のルールで翌々月払いだから」といった理由で、受け取りから60日を超えて支払うことはできません。自社の顧客からの入金が遅れていることを理由にするのも同様に違反です。
-
代金を不当に減額すること
受注側に責任がないのに、「販売協力金」「振込手数料」などの名目で、一度決めた代金から一方的に金額を差し引いてはいけません。
ちなみに、営業現場での安易な「協力依頼」が違反になることもあります。
例えば、発注後に営業担当者が「少し予算が厳しくなったから協力してほしい」といった曖昧な理由で値引きを要請する行為は、不当な減額にあたる可能性があります。
特に、受注側の合意なく振込手数料を差し引くのは、たとえ少額でも明確な違反です。
-
不当に返品すること
受注側に責任がないのに、一度受け取った製品を「お客様からキャンセルされた」などの理由で返品することはできません。
-
買いたたき
市場価格と比べて著しく低い価格を一方的に押し付けることが該当します。
例えば、原材料の価格が上がっているのに、十分な話し合いもなく価格を据え置く行為が該当します。
他にも、通常より極端に短い納期を要求する場合、受注側は追加コストがかかります。このコスト増を無視して通常価格で発注することは「買いたたき」にあたる可能性が非常に高いです。
また、複数の業者から見積もりを取り、その最低価格を他の業者に提示して「この金額でなければ発注しない」と一方的に通告することも、買いたたきと見なされる恐れがあります。
-
購入や利用を強制すること
取引を続けることを条件に、自社や関連会社の商品(お歳暮やおせち料理など)やサービスの購入・利用を強制してはいけません。
-
報復措置
受注側が、発注側の違反行為を公正取引委員会や中小企業庁などに通報したことを理由に、取引量を減らしたり取引を停止したりするなどの仕返しをしてはいけません。
-
有償支給材料の代金を早期に決済すること
発注側が提供した原材料の代金を、その材料で作った製品の代金の支払日より前に差し引くことは禁止です。
-
割引が困難な手形の交付
支払いに手形を使う場合、金融機関で現金化するのが難しいような長期間の手形(繊維業以外では120日を超えるものなど)を渡してはいけません。
-
不当な経済上の利益を提供させること
仕事の対価とは別に、金銭やサービスなどを不当に提供させることです。
例えば、「決算に協力してほしい」と協賛金を要求する行為が該当します。
他にも、「『お店が忙しいから手伝いに来て』と、従業員を無償で派遣させる行為」「長期間発注がないにもかかわらず、自社が所有する金型を無償で保管させ続ける行為」が該当します。
-
不当なやり直しや内容変更
受注側に責任がないのに、発注側の都合で仕様変更ややり直しをさせ、その費用を負担させると違反になります。
例えば、顧客からの急な仕様変更があった際、その追加コストについて受注側と協議せず、「ちょっとした変更だから」と無償での対応を強いるのは典型的な違反事例です。営業担当者は、追加費用について必ず事前に協議し、書面で合意する必要があります。
-
価格協議に応じず一方的に価格を決めること
原材料費や人件費の上昇を理由に受注側から価格交渉の申し入れがあったのに、正当な理由なく話し合いを拒否したり、説明もせずに価格を据え置いたりすることは、新たに禁止されました。
例えば、受注側から価格改定の相談を受けた際に、営業担当者が「上司に確認します」と言ったきり回答しなかったり、「うちは価格を変えない方針だ」と一方的に交渉を打ち切ったりする行為が、まさにこの禁止行為に該当します。誠実な協議のテーブルにつく姿勢が求められます。
-
手形払い等の原則禁止
受注側の資金繰りを圧迫する原因となっていた約束手形での支払いは、原則として全面的に禁止されます。これも新たに禁止されました。
まだ改正取適法が施行前にも関わらず、最近、「優越的地位の濫用」に対する摘発が報道される機会が増えた気がしませんか?
分かりやすく言えば、政府側(中小企業庁と公正取引委員会が中心)は、本気になっているのでしょう。その背景には、日本がかつての経済大国としての存在感を失いつつあるという焦りがあるのかもしれません。
例えば、世界に大きな影響力を与えるとされる企業「GAFAM(ガーファム)」(※Google(Alphabet社)、Amazon、Meta(旧Facebook)、Apple、Microsoft)には日本企業はなく、すべてアメリカ企業です。
日本がかつての輝きを取り戻すためには、「優越的地位の濫用」のようなつまらないこと(と、あえて申し上げましょう)でビジネスを滞らせている場合ではない──取適法は、こういった事情もあり、注目されているのです。
摘発されて、「今までは大丈夫だったのに...」と後から後悔しないよう、ぜひ取適法(旧下請法)に対する認識と理解をアップデートしておきたいものです。
【補足】冒頭に挙げたクイズの解説
既にご案内した内容と重複する部分もありますが、冒頭に挙げたクイズに対する解説を付記します。
- 「極めて短いリードタイムで見積書提出を求める行為」
→ 受注側がコストを適切に見積もる時間を奪い、結果として不当に低い価格での発注(買いたたき)につながる恐れがあります。
- 「通常納期よりも短期間での納品を求める行為」
受注側は残業や休日出勤などで追加のコストが発生します。
このコスト増を無視して通常価格で発注することは「買いたたき」に該当する可能性がとてもに高いです。
- 「深夜・早朝など営業時間外に連絡し、返事を急かす行為」
これ自体は取適法の直接の禁止行為ではありません。
しかし、営業時間外、つまりプライベートな時間にまで仕事を強要されることは、受注側の従業員にとって大きな負担を強いることになります。受注側の従業員からすれば、「この返事が遅れると、今後の仕事に影響が出るかもしれない」と強迫観念にさらされることもありますから。
よってこのような行為も、取引上の優越的な地位を利用した不当な要求と見なされ、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたる可能性があります。
- 「製品サンプルなどを強制的かつ無償で提供させる行為」
本来、受注側が負担する必要のない費用や労力を一方的に押し付ける行為であり、「不当な経済上の利益の提供要請」という禁止行為に明確にあたります。
- 「自社製品・サービスの利用を要求する行為」
取引継続を条件に自社製品の購入などを強制することは、「購入・利用強制」という明確な禁止行為です。